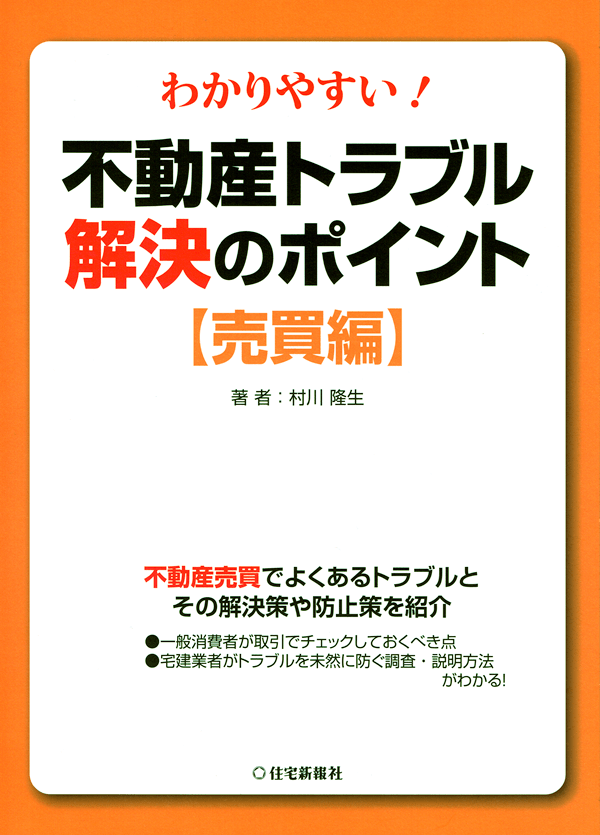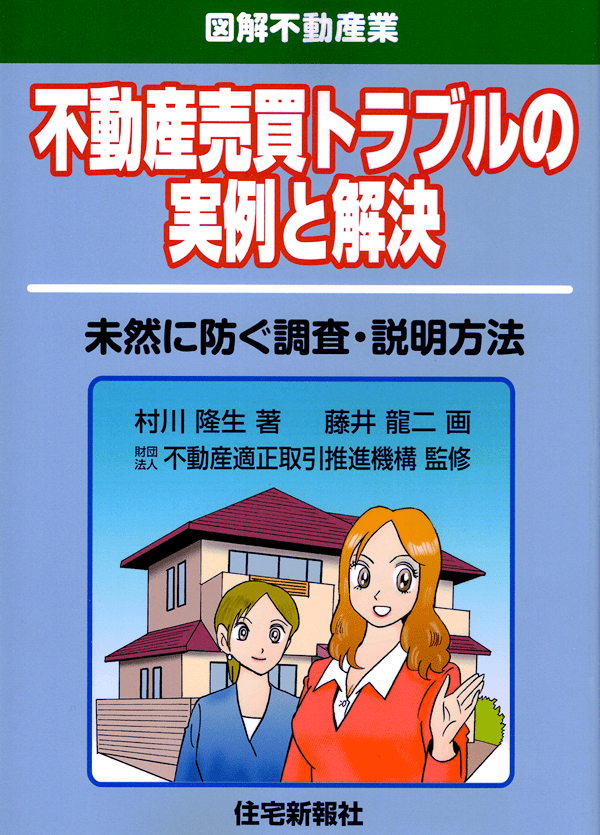中古住宅の売買契約において、宅地建物取引業者である仲介業者は、取引についての重要事項の説明を書面で行うことが義務付けられています(宅地建物取引業法35条)。
書面を交付して説明するというルールで、実際には「重要事項説明書」という書面を作成し説明します。
これは、対象物件および不動産取引に関してあまり知識がない一般消費者(買い手)を保護するため、売買契約の前に、仲介業者が買い手に対し対象物件についての最低限必要な情報を説明する制度です。
重要事項説明書は、対象物件および契約内容について、買い手が納得してから契約するための条件を書面に残しておく重要な書類です。
重要事項説明書は、売主と買主の売買契約書とは別ものですが、売買契約の有効性にも関連するのでとても重要なのです。
そもそも重要事項の説明とは
そもそも重要事項の説明とは、仲介業者の宅地建物取引士が、契約締結の前に説明する義務がある、重要な説明です。
一般的には、重要事項説明書としてまとめられ説明を受けます。
内容は、おおまかに「取引物件に関する事項」「取引条件に関する事項」の2つです。
取引物件に関する事項
- 物件の表示
- 当事者
- 登記事項
- 登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている情報
- 法令に関する制限
- 私道関する負担の有無
- 飲用水・電気・ガスの施設の状況
- 物件の形状など
取引条件に関する事項
重要事項の説明については一般財団法人 不動産適正取引推進機構の「これでわかる重要事項説明書」がとてもわかりやすいです。
これでわかる重要事項説明書
(財)不動産適正取引推進機構

実際の重要事項説明書の書式
実際の重要事項説明書の書式には、全宅連(全国宅地建物取引業協会連合会)、公益社団法人全日本不動産協会などの業界団体のフォーマット、仲介業者独自のフォーマット、市販されているフォーマットなど様々な書式があります。
国土交通省が重要事項説明書の標準書式を提示しています。
このように、重要事項説明書には、「売買物件の物理的な条件や権利関係を調査した内容」「売買契約の条件」などがまとめられています。
重要事項の説明(重要事項説明書)に関連する買い手側のリスクヘッジ
重要事項の説明(重要事項説明書)については、買い手側のリスクヘッジとして、下記の6点くらいは気を付けておかれることをおすすめします。
重要事項説明書は契約日に先立ち入手し契約日とは別の日に説明を受ける
上記でも説明していますが、重要事項説明書は、契約日の1週間くらい前には入手し確認しておくことをおすすめします。
できれば、前もって契約日とは別の日に重要事項の説明を受けるようにしましょう。
重要事項の説明(重要事項説明書)でわからない言葉や内容は理解できるまで質問する
重要事項説明書の説明には、日常生活では使わない専門用語や法令用語が使われています。
不動産のことをあまり知らない一般の方は、わからなくても当然です。
また、ひととおりの説明はあっても、一般の買い手にとって、それが何を意味するかの説明が不十分なことがあります。
わからないことは、言葉についても内容についても、理解できるまで業者さんに聞きましょう。
重要事項の説明(重要事項説明書)では買手のデメリットこそ積極的に確認する
買い手側が対象物件を気に入っている場合は、マイナス点はあまり聞きたくないバイアスがかかりがちになります。
そのような場合こそ、買い手自身にとってマイナス点、デメリットになる点についても積極的に確認しましょう。
一方、仲介業者は、常に取引を成立させたい動機があるので、こちらも買い手にとってのマイナス点はあまり積極的に説明したくないバイアスがかかりがちになります。(^^;
買い手側は、聞きたくない事実でもしっかり確認しましょう。
仲介業者の口頭での説明や回答は事実なのか担当者の意見なのかを見極める
とくに仲介業者の口頭での物件説明では、役所などで確認された事実なのか、それとも、説明する担当者個人の憶測や推測なのかを、見極めましましょう。
仮に、説明する担当者の個人的な考えや推測の場合、たとえさらに調査する時間がかかっても、再度確認してもらいましょう。
また可能な限り、買い手自身が役所へ出向くなりし確認しましょう。
物件の購入条件や購入動機については事前に仲介業者に詳しく説明しておく
希望の物件を仲介業者さんに探してもらう際、購入条件や購入動機については、仲介業者さんに詳しく伝えておきましょう。
聞かれていない項目についても、主体的に伝えておくのをおすすめします。
あまり希望項目が多すぎても、該当する物件が見つからなくなってしまいますが、絶対に譲れない項目は、書面に残し双方で確認しておくのが無難です。
もちろんこれは、希望に近い物件、希望どおりの物件を探してもらうためでもあります。
さらにより重要な点として、依頼者の個人的な意向について知った仲介業者さんは、その意向に応じた重要事項の説明義務が発生するからです。
仲介業者さんの説明義務がより明確になるからです。
重要事項の説明(重要事項説明書)のフォーマットが最新かどうか確認する
宅地建物取引業法は随時改正され、重要事項の説明すべき項目も随時追加されています。
そのにともない重要事項説明書の項目も随時追加されている必要があります。
ところが、仲介業者さんの中には、慣れなどの理由で必ずしも最新の説明項目が記載されていないフォーマットの重要事項説明書を使っている場合があります。
そもそも、重要事項説明書の書式には、全宅連(全国宅地建物取引業協会連合会)、公益社団法人全日本不動産協会などの業界団体のフォーマット、仲介業者独自のフォーマット、市販されているフォーマットばど様々な書式があります。
特に市販されているフォーマットは不備が多く、これを使っている仲介業者さんで行政指導・処分を受けた宅地建物取引業者さんも少なくないのが現状です。
よって、重要事項の説明(重要事項説明書)のフォーマットが最新かどうかの確認も重要です。
平成30年4月1日に施行される宅地建物取引業法と重要事項説明書のインスペクション関連部分
平成28年の宅建業法の改正によって、平成30年4月1日から施行される宅地建物取引業法では、中古住宅(既存住宅)の売買時、仲介業者さんの説明内容にも追加事項があります。
中古住宅(既存住宅)の売買プロセスにおける新たな説明の内容とタイミングは下記がわかりやすいです。
これにともない平成30年4月1日以降の重要事項の説明では、インスペクション関連部分にも注意しなければなりません。
そもそも、新たに追加されるインスペクションの説明箇所は、中古住宅の流通を活発化させる目的で追加されています。
中古住宅の購入を検討されている場合は、必須の確認項目です。
下記がインスペクションに関連する追加の説明項目です。
- 媒介契約書面の記載事項に、建物状況調査を実施する者(インスペクション)のあっせんに関する事項を追加
- 重要事項説明の対象に、建物状況調査(インスペクション)の結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を追加
- 宅建業者が売買等の契約当事者に交付する書面の記載事項に、建物の構造上主要な部分等の状況について、当事者の双方が確認した事項を追加
よって、重要事項説明書でも建物状況調査(インスペクション)の項目が必要になります。
建物状況調査(インスペクション)の項目が重要事項説明書にしっかり記載されているかどうかも平成30年4月1日以降の注意点です。
重要事項説明書に関連するトラブルの事例
重要事項説明書の注意すべきポイントは、重要事項説明書に関連する具体的なトラブル事例を知ることでより理解が深まります。
参考に、不動産適正取引推進機構のWEBサイトと参考書籍をご紹介します。
不動産適正取引推進機構の紛争事例データベースの「重要事項説明に関するもの」
重要事項説明に関する紛争事例は具体的な事例が豊富です。
↑重要事項説明に関するものとして下記の内容が解説されています。
都市計画等の法令上の制限
-
- 都市計画道路の計画線誤表示をめぐるトラブル
- 区画整理事業地内の道路拡幅不告知をめぐるトラブル
- 市街化調整区域内の土地の説明義務
- 連棟式建物の売買の説明義務
- 接道要件を具備しない宅地についての金融機関の説明義務
- 航空機騒音の告知義務
- 市街化調整区域についての虚偽の説明
- 建築制限に関する事項の不告知
- 住宅の建築ができない土地の売買
- 土地建物の問題点
-
- 越境物の不告知等をめぐるトラブル
- フローリング工事不可の不告知をめぐるトラブル
- 車庫に関する不十分な説明をめぐるトラブル
- 水道等についての説明不備
- 前面道路の説明の誤り
- 隣接地への越境等の説明
- マンションの方位についての説明義務
- マンションの設備騒音と意思表示の錯誤による契約の無効
- 防火扉の操作方法等に関する説明義務
- 雨漏り及び敷金の承継の説明不備
- 土壌汚染に関する説明の未実施
- 土壌の来歴や従前の使用方法の説明義務
- 眺望・日照・周辺環境等
-
- ごみ置き場に関する重説ミス
- 近隣牧場の悪臭の不告知をめぐるトラブル
- 隣地マンションの新築による日照阻害によるトラブル
- 浸水被害と媒介業者の調査義務をめぐるトラブル
- 水管橋工事の予定不告知をめぐるトラブル
- 隣地住人からのクレームが予想される用途であることについての説明不備
- 隣地の高架道路建設計画の告知義務
- 隣地の建築についての虚偽の説明
- 周辺道路計画の告知義務
- 隣地の建築計画の秘匿
- 青田売りマンションの完成後の状況を説明する義務
- 入居後間近かに高さ5mの要壁が建築された
- 隣人とのトラブルについての媒介業者の説明義務
- 眺望を売り物としていたマンションの売主の説明義務違反
- その他
-
- 差押えについての説明不足
- 租税特別措置法の誤った説明
- 不完全な工事見積書を交付した媒介業者の責任
- 売主のなした裁判上の和解と不知の買主の責任
- 価格検討上の重要な事実の売主の説明義務
- 売主が調査を拒否した事実についての媒介業者の責任
- 滞納管理費及び修繕積立金の説明不備
- ペット飼育禁止の不告知
重要事項説明書に関連するトラブルの事例の参考書籍
住宅新報社さんから出版されてる「わかりやすい!不動産トラブル解決のポイント【売買編】」「不動産売買トラブルの実例と解決(図解不動産業シリーズ)」の2冊です。
図解不動産業シリーズがはマンガで解説されているので、一般の方にも理解しやすいと思います。
双方とも内容のほとんどは「重要事項説明に関するトラブル」の事例ですので、重要事項説明書の理解にとても参考になります。
個人的には「わかりやすい!不動産トラブル解決のポイント【売買編】」をおすすめします。こちらは「不動産売買トラブルの実例と解決(図解不動産業シリーズ)」の内容をもとに1事例が1ページにまとめられていて見やすく要点がわかりやすいです。
- 序章 トラブルの原因と未然防止
- 第1章 禁止行為に関するトラブル
【事例数8】
- 第2章 重要事項説明に関するもの
【事例数28】
- 第3章 売買契約の解除に関するもの
【事例数4】
で圧倒的に「重要事項説明に関するトラブル」の事例が多いので、とても参考になります。しかも税込514円です(^^)
わかりやすい!
不動産トラブル解決のポイント【売買編】
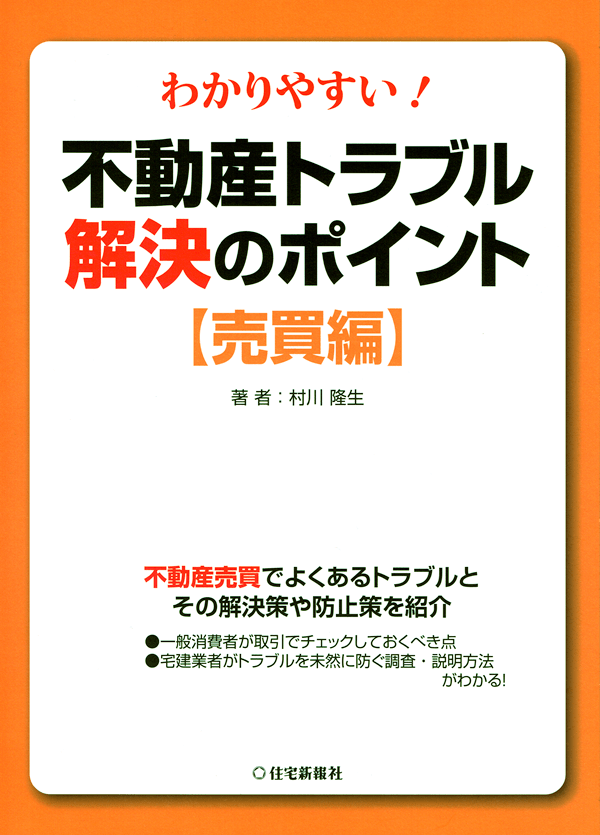
【出版社の説明より】
不動産売買でよくあるトラブルとその解決策や防止策を紹介。一般消費者が取引でチェックしておくべき点、宅建業者がトラブルを未然に防ぐ調査・説明方法がわかる!
不動産売買トラブルの実例と解決
(図解不動産業シリーズ)
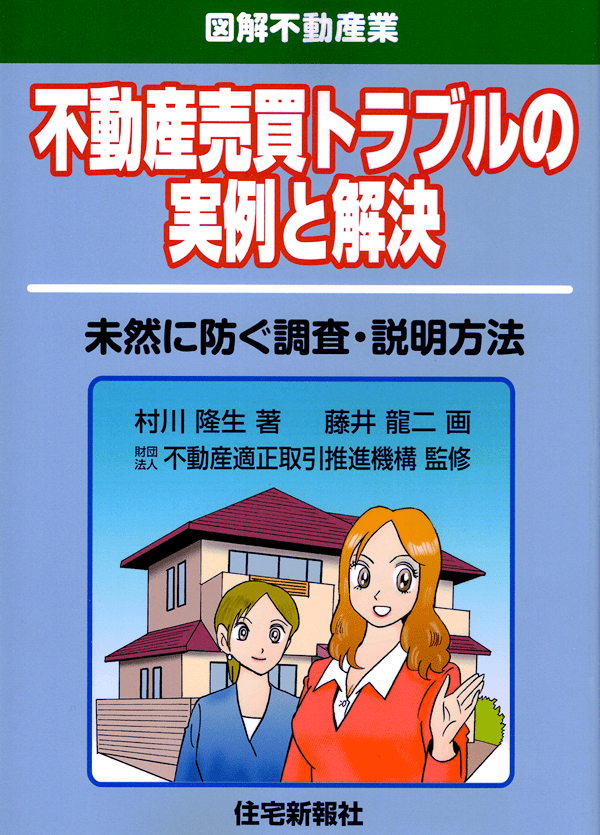
【出版社の説明より】
不動産会社に勤めたばかりの従業者でも、取引でのトラブルを未然に防ぐための調査や説明方法、宅建業法の規制、トラブル解決への考え方をわかるようにまとめている。
重要事項の説明(重要事項説明書)は、買い手にとっては、文字通りとても重要なはずなのですが、一般の買い手側もはじめて目にするケースが多く、どこに注意すればよいかもわからない場合が多いと思います。
一方、すべての仲介業者側が、事前に、買い手側に重要事項の説明(重要事項説明書)の重要性を十分に説明しているとは限りません。
よってこれも買手側のリスクヘッジとして重要事項の説明(重要事項説明書)の内容は、十分に慎重に確認されることをおすすめします。